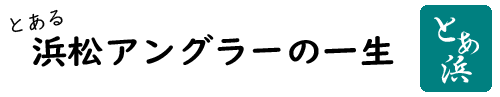シマノの17年次世代リールのはじまりは、耐久力に定評のある「ツインパワー」が登場。(現在は2021版が登場しています!)

「耐久性の基準を変えてしまう」とか、前モデル以上に強くするとか頭おかしいんじゃねぇの?
発表後に沸き立つソルト界を他所に、いまいち魅力は感じられなかった。
良さより突っ込み所が多いので、なるたけ活かす方法を考えた結果、「ツインパワーXD」として生まれ変わったリールを、主観だだ漏れで紹介。
この記事のまとめ:
シマノの「ツインパワーXD」は、前モデルを超える強度と耐久性を誇る次世代リールです。特に「HAGANEギア」が採用され、ギアの耐久性が向上していますが、ギア以外の部分が脆いと全体の強度には限界があるため、これが万能解決策とは言えません。また、「Xプロテクト」防水構造が新たに導入されていますが、複雑な構造は生産や修理のコストを上げる可能性があります。最も多いトラブルとしては、ラインローラーの塩ガミが挙げられ、これは使用後のメンテナンスが重要です。ツインパワーXDの強度は大物相手に適しており、特に磯での釣りに最適ですが、あまりに強力なギアや防水機能は過剰装備とも言えます。それでも、リール全体の性能は非常に高く、購入する価値は十分にあります。
とにかく強い!(小並感)を全面に押し出したツインパワーXD
前置きしておくと、これはむしろ良すぎるリール。

買って損はないでしょう。
でも「これいる?」と感じる点があったから、そこにツッコミを入れたい記事です。
シマノは『HAGANEギア』をやたらと推すけど、ギアの耐久だけ向上されても……。
それ以外に耐えられない部分が多いからね。
タックルには金属を使えない箇所があり、リールより脆い部分は多い。
リールはもともと強固な物。
ギアを強くするメリットは「ゴリ巻き(力押し)」にあるけれど、全力で逃げる大物相手に、ドラグを出さず耐えれるロッド、切れないラインシステムがまず存在しません。

──みたいなチグハグを感じる。
『NEWツインパワー』の初期ラインナップは3000・5000番で、ショア向けの小型がメイン。
強さを全面に出すなら──

「マグロ100kgもゴリゴリでイケましたよ! HGNギアまじヤバイっすね!」
くらいのアピールで、SWモデルの10000番台を最初にだね。
総合的に見れば悪い点はないし良すぎるくらいだが
ツインパワーXDのお値段は49000円前後。
リール全体の耐久性は業界随一であるし、ローター部は最軽量のヴァンキッシュに迫るスペック。
何回“他のリールが過去”になればいいのやら。
マイクロモジュールギアを入れなかったのは、絶対的な強度を得るためだろう。
大口径のギアを活かすのならば、あれは無用の長物ともいえるし、差別化としていい選択でしょう。
ただそれを活かせるファイトをしているアングラーは、どこで戦っているかを考えると──
ロックショアを主戦場にしている人たちくらいだろうな、と思う。
新構造の防水構造「Xプロテクト」について
これを見て「スゲェ!」より「バカじゃねぇの」と思ったのは私だけだろうか。
入る水が海水なら、出にくくすれば錆びるだけじゃねーのと。
内部で塩が結晶化して排水できなくなるとか、内部が腐食してボロッともげる未来がありそう。
わざわざ複雑な構造にして、生産と修理のコストを上げるのもバカらしいと思う。
防水構造の「コアプロテクト」は、浸水しにくい構造なだけで、完全な防水じゃない。
完全防水にするには、水の分子が入れない隙間かつ、可動させる必要があるわけで、無茶ブリもいいところです。
リールの場合、ハンドルを回すと内部からエアーが吹き出て「自然乾燥機能ですけど?」くらいが面白いと思う。
TPは買いだけどラインローラーは釣行のたびに洗おうね
ステラで最も多いトラブルが、ラインローラーの塩ガミ。
これはハッキリいってユーザー側が悪いだけ。
開発側からすれば「釣行後に洗えよ」とキレ気味にいうだろうけど、防水構造にした悪影響も要因にある。
ようするに、水が入りにくいってことは出にくいってこと。
メンテナンスフリー(笑)のマグシールドでさえ、この問題は解決しておらず、海釣りの天敵はいつだって塩である。
機械は単純構造のほうが修理もしやすく、誰でもメンテナンスしやすい。
よって「物持ちがよくなる」メリットがある。
わざわざ複雑化してコストを上げる選択をとるのは、日本企業の悪いクセ。
まあリールに関わる技術で、客を刺激する明確な違いは、軽量化と剛性アップしかないしね。
この選択はしょうがないって、私はわかっているから(生暖かい目)。
ツインパワーXDのスペックが最大限に活かせるポイントは磯くらいでは?
10kgクラスのアカエイ番長でも、ドラグを出しつつロッドが折れなければ、なんとでもなります。
ツインパワーXDのスペックをフルに活かす指標は、そういう重いヤツをドラグを出さずに巻きで寄せることでしょう。
ほならね、「大間のマグロ釣り」を参考にしてみたらどうでしょう。
ようは大物相手にロッドを使うのは非効率です。
それが「ゲームフィッシング」といわれる所以でもあるし、難しいから達成感のある行為。

──法律で定められているってのもあるけど。(遊漁的な意味で)
よくある質問(FAQ)と回答例
Q1: 「ツインパワーXD」は他のリールと比べてどのように優れていますか?
回答: 「ツインパワーXD」は、特に耐久性と強度に優れたリールです。シマノの「HAGANEギア」と「Xプロテクト」防水構造が採用されており、これによりリールの長寿命化と耐環境性能が向上しています。特に、磯での釣りや大物狙いの際にその強さを実感できるでしょう。
Q2: 「ツインパワーXD」の「HAGANEギア」とは何ですか?
回答: 「HAGANEギア」は、シマノ独自の冷間鍛造技術を用いたギアで、従来のギアに比べて非常に強靭で耐久性があります。これにより、リールのスムーズな操作感を長く維持することができます。
Q3: 「Xプロテクト」防水構造の利点は何ですか?
回答: 「Xプロテクト」は、リール内部への水や塵の侵入を防ぐ構造で、特に海釣りにおいて効果的です。この構造により、リールの内部機構が保護され、長期間にわたりスムーズな動作を保つことができます。ただし、防水機能が高い分、メンテナンスが必要な箇所もあり、定期的な手入れが推奨されます。
Q4: どのような釣りに「ツインパワーXD」が適していますか?
回答: 「ツインパワーXD」は、特に大物狙いの磯釣りや、ショアジギング、ロックショアなどの過酷な環境での釣りに適しています。その強度と耐久性により、大物とのファイトでも安心して使用できます。
Q5: 「ツインパワーXD」の価格は他のリールと比べて高いですか?
回答: 「ツインパワーXD」は、非常に高性能なリールであり、その分価格も他のリールに比べて高めです。しかし、耐久性や性能を考慮すると、その価格に見合った価値があると言えます。釣行頻度が高い方や、大物狙いの釣りをされる方には特におすすめです。
Q6: 「ツインパワーXD」のメンテナンスはどのようにすればよいですか?
回答: 「ツインパワーXD」のラインローラーなど、塩ガミしやすい部分は特に注意が必要です。釣行後は、真水で洗浄し、しっかりと乾燥させることが重要です。これにより、リールの長寿命を保つことができます。また、定期的なオーバーホールもお勧めします。