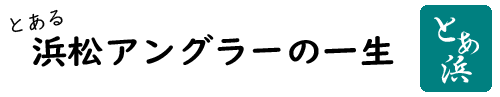キャスティングの飛距離をなるべく簡単に測る方法をまとめてみました。
この記事のまとめ
キャスティングの飛距離を測る方法について簡単にまとめました。サーフルアーの釣りで遠投が有利とされる中、飛距離を正確に測定することは、釣果を上げるための重要な要素です。飛距離測定のメリットは、ルアーの性能を把握し、釣りのメソッドを組み立てやすくすることにあります。
ルアーの飛距離を測る方法は、「計器を用いる」か「目測」の2つです。計器を使用することで、ルアーの飛距離を正確に知ることができ、その情報を基に釣りの戦略を練ることができます。例えば、70m飛ぶルアーを正確に飛ばすことで、その距離にいる魚を狙いやすくなります。
さらに、スマートフォン用のレーザー測定器「iPin PRO」を使えば、簡単に飛距離を測ることができます。
キャスティングの飛距離を測るメリットはどこにある?
特にサーフルアーは空前の飛距離ブーム!
遠くに飛ばせたほうが有利になる釣りは多い。

でも実際のところ……、「それほど意味なくね?」と気づきます。
より重要なのは、魚が居る場所に投げ入れる精度だと──。
さてさて、ルアーの飛距離を測る方法はふたつあり、「計器を用いる」か「目測」のどちらか。測定するかしないかは個人の自由ですけど、測定するメリットは共通します。
- 「このルアーはこれだけ飛ぶ」の指標ができること
- 飛距離を理解することでメソッドの組み立てがしやすくなる

ひとつずつ説明しましょう。
「このルアーはこれだけ飛ぶ」の指標ができること
ルアーのパッケージにはよく「○m飛ぶ!」みたいな表記がありますよね。
例えば70m飛ぶルアーをきっちり70m飛ばせるなら、表示法違反ではないし、あなたのタックルが可怪しいわけでもないとわかります。
もし70m以下しか飛ばなかったら……? 悪いのはメーカー? それともアングラー側?
ロッドには投げるに適したルアーウェイトがあり、「○~○gまで」などとカタログか本体に表記されています。まずはそれを守ることが大事。適したロッドを使えば、ルアーはメーカー発表通りに飛びます。
意図通りに飛ばせるなら、70m飛ぶルアーは70m前後まで飛んでくれるとわかります。
その着水点を70mと覚えれば、「あそこが70mかぁ……」などとおぼろげに体感できるわけです。
飛距離を理解することでメソッドの組み立てがしやすくなる
70m飛ぶルアーの性能をキッチリ引き出すことで、「0~70m」の範囲に居る魚を狙えることになります。
50mの位置に落としたいなら、フルスイングより弱く振ればいいし、サミングで調整することもできます。それ以下ならほんと軽く投げるだけになりますね。
別に正しく距離を測る必要はありません。おおよそでいいから、70m飛ぶルアーはあそこまで飛ぶだろうという認識を持つことが大切。
どのルアーもキャスティングに使う力はほぼ一定。
5gでも15gでも40gでも……使うべきロッドの規格が変わるだけで、最大飛距離を出せるスイングスピードは決まっています。
ルアーは大きさや形状よりも、ウェイトが飛距離を出す大切な要素であるため、「○gはこのロッドなら○m飛ぶ!」みたいな指標ができあがっていきます。
機械1つだけでルアーの飛距離から魚の体長まで測れる時代に
今はスマホを使い、写真を撮るだけで被写の長さを表示するアプリもあります。より正確に測るためには、スマホにオフセットできるこんなデバイスもあります

「iPin PRO」はスマホに取り付けるだけで、あらゆる寸法が測定できるようになります。
レーザー測定器は建築分野でも使われるし、地味に高価……。
iPin PROなら1万ちょっとで高性能なレーザー測定ができるため、かなりお得といえます。
レーザーは室内空間など、固定された物体の寸法を測れることに長けています。
でもおおよそでいいなら、魚の体長を測ることもできるし、あのナブラまで何メートル先にあるのかを知ることもできます。
キチンとルアーの飛距離を測定するなら平地で
メーカーが公表するルアーの飛距離は、屋外の平地でテストすることが多く、実測は巻き尺を用いることが多いです。
巻き尺は陸上競技のライン引きで使うアレですね。
この場合、単独よりも2人で測定することが望ましく、ボッチには辛いところがあります。1人でもルアーの飛距離を測定したいのなら、ゴルフ向けのレーザー距離計を使うのがオススメ。
使う際のポイントは、測定器を三脚かなにかで固定すること。光線がブレるだけで距離測定が雑になりますので……。