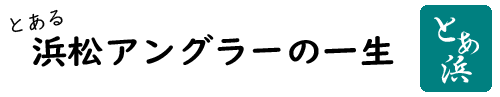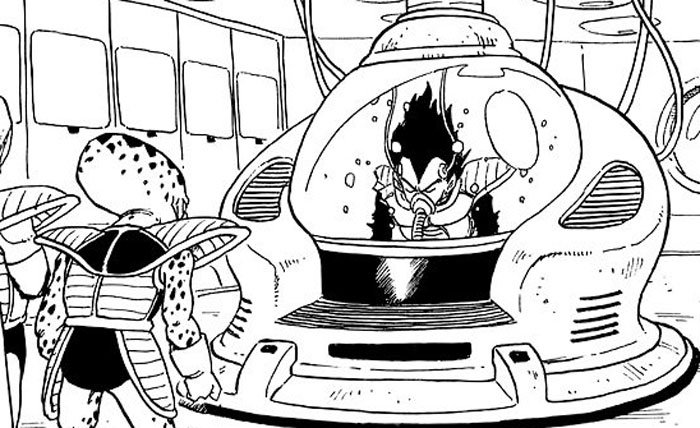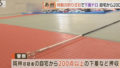細胞から魚肉を作る目標のスタートアップがある。
培養肉があるくらいだから、いまさら培養魚で驚くことはないが……。
問題はその肉を、日本は受け入れることができるのか、にある。
刺し身が食べたければ筋肉を培養すればいいじゃない
魚肉の培養に関しては、次の記事を参考にしてください。

「なんで魚肉を培養しようと思ったの?」に関しては、次のように理由が述べられています。
1.魚は健康にいいが、世界中で消費が伸びたことで消費量が生産量を上回り、価格が高騰している。そしてこのままいくと近い将来、魚が取れなくなる可能性がある。
https://media.dglab.com/2017/09/19-event-indiebio-01/
2.環境汚染により、魚に水銀やプラスチックが含まれる場合があり、健康を害することがある。
知っての通り、近年はあらゆる魚が不漁続き。
世界の魚資源も減りつつあり、いっぽうで人口は増え続けている。いずれも何も、世界の食糧難はすぐそこに迫っているわけで、安全に早く生産できる培養肉に注目が集まっている。
培養肉を食べることに対して、オーガニック食材信者は卒倒する可能性が高いでしょう。しかし、天然よりも食品に安全が確保されていることも知っていもらいたい。
自然界には細菌が存在するし、完全なる安全食は存在があやふや。コウモリ食べてアレが蔓延したかも……な今の世。身にしみているでしょう。
魚肉培養が低コスト化すれば…?
近頃は山間で養殖することが定番化しています。なぜかといえば、水が綺麗で豊富だから。
陸上の養殖は水を確保すればどこでもできるけど、儲けを出すには広い土地と施設が必須なので、初期投資からの失敗が特に怖い分野。
いっぽうで魚肉の培養は、タワーマンションの全室を食品工場にできるから、都市部でも生産できることがメリット。
どうやって肉を培養するのかっていうと、サイヤ人を回復させるアレのイメージでほぼあっています。
ゆくゆくは宇宙ステーションでスシパーティもできるようになるかも。
培養肉は人間が地球外に長期間出るためにも必要になります。宇宙旅行も金さえ積めば民間でも行けるようになりましたしね。

うな次郎みたいな代替品が代替のようで代替じゃなくなるかも?