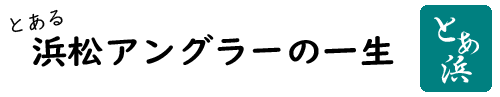釣りをしていると、魚を活け〆している姿を見かけます。
「鮮度が良い=美味い」と信じてやまない人が多いですが、血抜きや神経締めなど「活け締め(活け〆)」は、やるべき魚とやらなくてもいい状況があります。その根拠を知らない人が結構多い。
より美味しく食べたいのなら、最適な締め方と保冷を考えて実行すべきです。
【活け〆】血抜きと神経締めの違い
活け締めの方法は「血抜き」と「神経締め」があります。
それらを「魚を締める」と呼びますが、なぜするのかと釣り人に聞くと、「美味しくなるって聞いたから」と答えるのが大半かも。
今記事は「血抜きvs神経締め」のどっちがより美味いか論争に注目しつつ、それは基本で大事なことは他にもありますよ? をまとめました。
血抜きをするメリットとデメリット
血抜きをするメリットは、臭みを身に移さないこと。
死後硬直が進むほど血液は凝固するので、鮮度がいいうち(釣りたて)済ませるのがベター。するとしないとでは、生臭さが違います。
もっとも効率的なのは、心臓が動いている時にすること。
心臓は血液を送るポンプの役割があります。活きているうちに太い血管を切ると、水に浸けておけば勝手に血が抜けていきます。
とはいえ、”血を完全に抜く目的”を達成することは難しい。
水に浸けて血を溶かすほうが効率はいいけど、水がないとできないもどかしさもありますね。
- ナイフやハサミがあればできる
- 釣り場でもやりやすい
- 血を完全に抜くことは難しい
神経締めをするメリットとデメリット
神経締めをするメリットは、死後硬直までによけいな栄養分を消費されないようにすること。
血抜きだけでは体を動かせるため、捌くまでに筋肉から栄養を少なからず消費します。繊細な違いですが、食味にも影響します。
そのため、”極上の鮮度”を維持する目的なら、神経締めがベターですね。
デメリットは、専用の工具(ワイヤーなど)が必要になること。
神経締めの方法は、魚の中骨(一番太い骨)にある髄液を抜くことが基本。ほとんどは眉間に切り込みを入れて、そこからワイヤーを通す方法ですね。
慣れれば血抜きより速く済みます。暴れることがなくなるため、輸送で互いに傷つけないようにする処置でもあります。
……お気づきでしょうけど、神経締めをするだけでは血液が抜けないため、臭いは残りやすい点も見逃せません。
- (慣れれば)血抜きより手軽で速い
- 水揚げ後に”旨味”が減少しにくくなる
- 専用の工具と知識が必要
- 神経締めだけでは血は抜けない
「究極の活け締め」はあるけど、釣り場でするのは難しい
近年は神経締めができるアングラーも多くなりました。
いっぽう、釣り場でやれることには限界があります。「完璧な活き締め」をするためには、相応の道具と場所が必要になります。
ここで実際に、最善の活け締めを映像でみてみましょう。
完璧な血抜きをするには、血管に残る血液を、水圧で洗い流すことが最善の方法。……こんなの釣り場で無理やん。
釣った魚は「血抜きを優先」するべき理由
魚の生臭さの原因は「内臓」にあります。
血抜きをする過程で、首と尾を切ることになりますが、ついでに内臓を除去することで、臭みの原因をほぼ取り去ることができます。
神経締めは魚を切らなくてもいいため、簡単で速いことがメリット。でもそれは血抜きの観点だとデメリットになります。
釣った魚は活きているため、血抜きをしやすい状態。だから道具もハサミ程度で済む血抜きを優先するべきです。
【難題】血抜きと神経締めどちらがより美味いのか?
ここまで血抜きと神経締めについてまとめましたが……、はたしてどちらがより美味いのだろうか。
これ実は、答えが人それぞれになります。
刺身など生で食べるなら、臭みを軽減できる血抜きが最善。ジビエ料理にも通じるところがありますね。
素材の味を活かすなら、神経締めをしたものが望ましいでしょう。臭みを”風味”に使う目的なら、こちらが最善かもしれません。
などの理由により、「どちらが美味いか?」の答えは、料理する側の目的次第で異なる──みたいな感じになります。
- 美味さの基準は人それぞれ
- 調理目的で向き不向きがあるため、議論としては不毛
- ぶっちゃけ、両方やればいいよね?
【まとめ】血抜きと神経締めはそれぞれ得意な土俵がある
”活き締め”は目的があってこそ、最善を選ぶことができます。
血抜きと神経締め、どちらもメリットとデメリットがありますし、最善は「両方やること」です。
大量の魚を活け締めする必要があったり、長距離(長時間)輸送の目的があるなら、神経締めをしたほうがいいでしょう。
朝でかけて夕方戻る程度など、当日以内の短時間釣行なら、血抜きをするだけで十分ですね。……むしろ家に着いてからでも遅くありません。
「どちらがより美味いか?」については、優劣をつけがたいですけど、活き締めの時点で血抜きも神経締めもやったほうが、より美味くなりやすいことは確実です。
- 血抜きと神経締め、両方やってこそ最高の活け締め
- 白身は血抜きを優先するべき
- 赤身(青魚)は神経締めを優先するべき