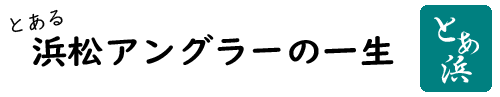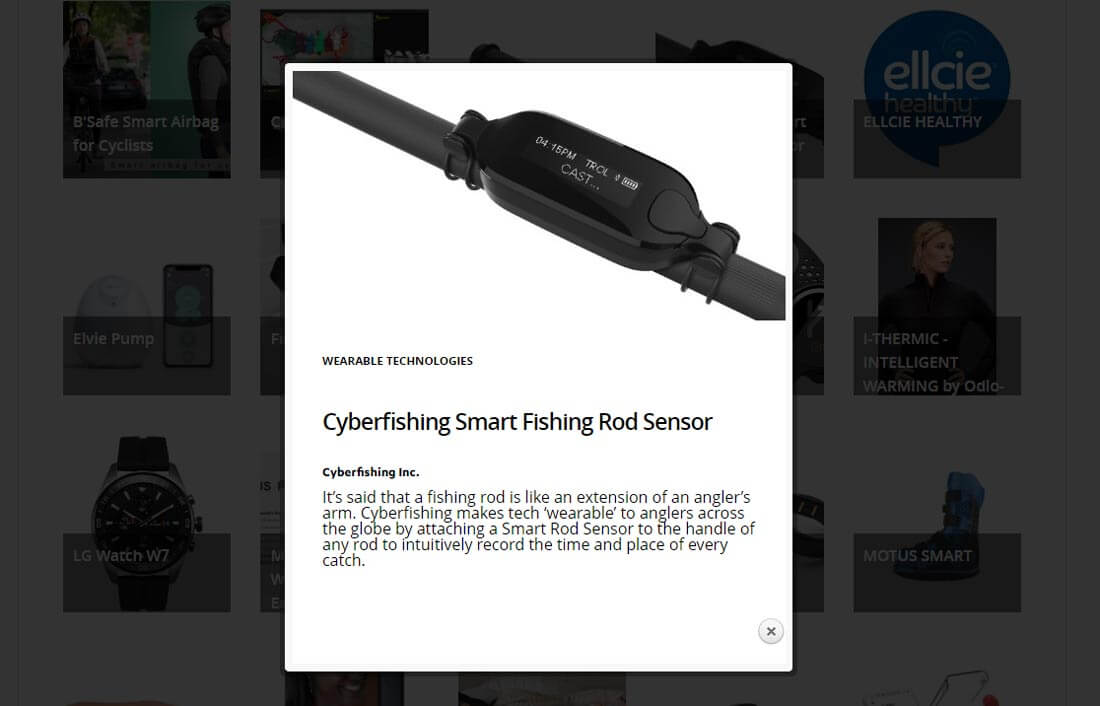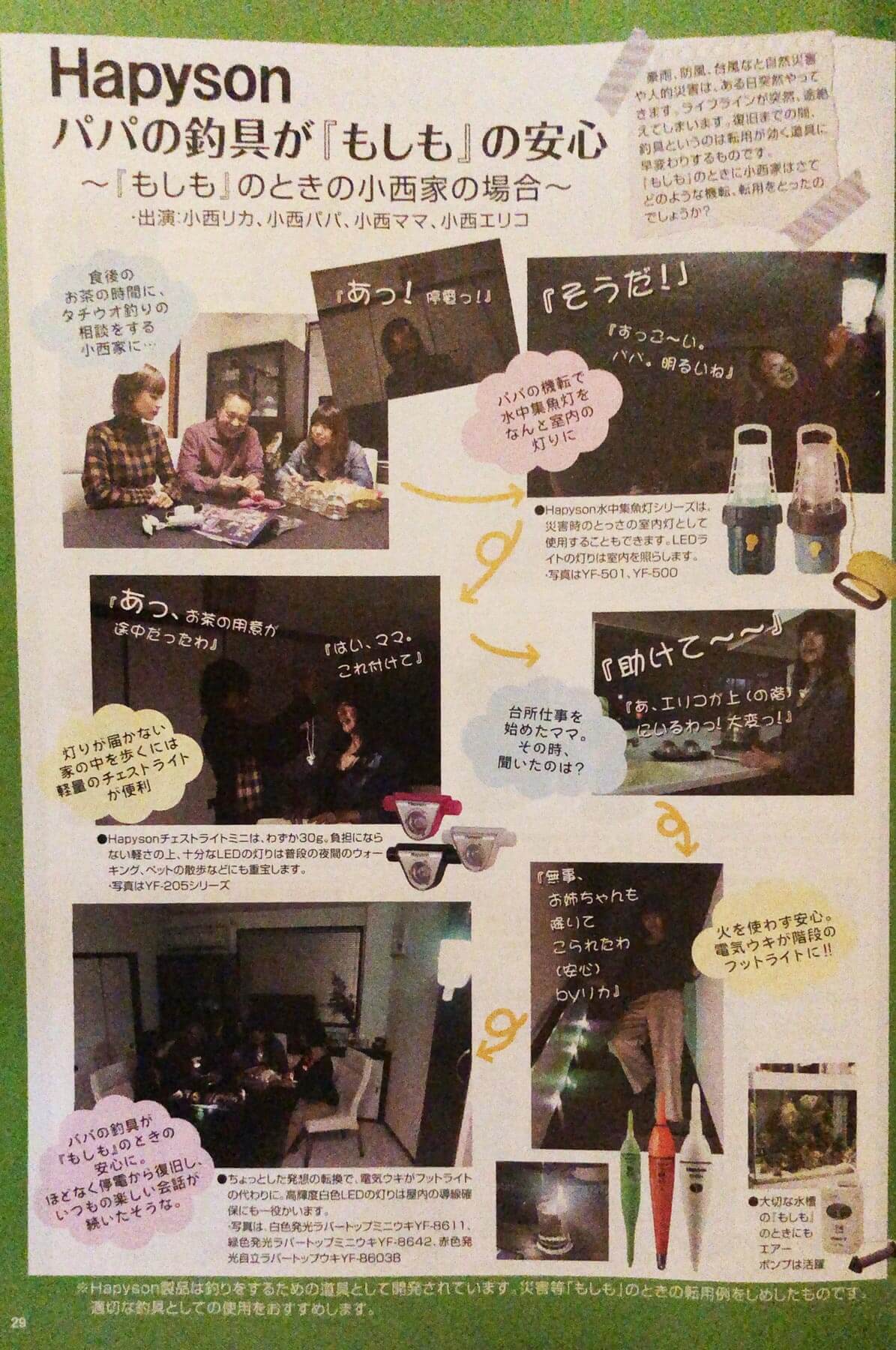大阪FSで「未来を感じる!」とか「これから来る!」と感じたモノを集めてみました。
これらの中でも一際ビビッときたのは『Cyberfishing』。
なぜ日本でこういう技術が生まれにくいのだろう。その答えは、多くのアングラーが無自覚で行っていること。
やはりというか、ITに関する釣具は全然なかったのが残念でした。
CES2019から大阪FSに来た「Cyberfishing」
「Cyberfishingって何?」を説明すると、釣り情報のデータ収集と共有を同時に行うモノです。
ようするに、「どこそこでこんな魚が釣れたよ!」などの釣り情報を、ロッドに装着したセンサーが自動で収集してくれるわけ。
ロッドにスマートウォッチを着ける感じで、全然邪魔にもならないです。
これを全てのアングラーが装着することになれば、釣り情報を扱う雑誌は商売あがったりかもしれません。逆にそのデータを利用して全国版を作るのも簡単になります。
ただユーザー数が少ないとデータの意味がありません。
外国の製品だしマニュアルも何もかも英語。なので「英語がわからないからうーん星ひとつ!」も普通にありそう。
日本国内に浸透するのは代理店が出来てからだろうなぁと。
釣りのITデバイスとしては『Deeper fishfinder』が有名でしょう。
こちらも出店しており、片言の日本語でパンフレットを渡してくれました。
もともと春先に買うつもりだったから、現物を見れたのは嬉しかった。
CES2019で革新的デバイスとして受賞している
向こうだと「やべーなこれ! すげーよ!」と絶賛されていそう。
それが日本に来ると、言葉の壁も少なからずあるけど、それほど必要としてない感じがします。

領収書をエクセルに落とし込んで計算するか、そのまま電卓で打って計算するか。
結果が同じであれ後者に慣れすぎた日本は、便利な情報技術に異様な拒否反応を起こすんですよね。
どこでも描ける発光ペイントの「CYALUME PAINT」
大阪FSで最初に引き寄せられたのは、暗闇でも発光するペイントを、噴射して文字を書いたり塗布したりすることがスプレーの「サイリュームペイント」です。
これ実は、技術的に世界初らしい。
制作したのは株式会社ルミカ、夜釣りのお供に定評がありますよね。
主な使用用途は、災害につきものの大規模停電時など。
夜でも光る文字で案内をすることができるから、避難誘導時に使えます。
都市部はガス漏れが懸念されるから、火を使う灯りが使えなくなることも……。光るペイントなら、そんな時でも迷わず使えるから有能ですね。
サイリュームペイントの発光時間は約4時間。釣行に使うには十分かと。
夜釣りで光らせたい所に塗布できるから自由度が高い
例えば投げ釣りで、穂先にケミホタル的な物をつけたい時──
サイリュームペイントは塗れば光るから、ケミホタルを装着するアタッチメントが要らなくなります。……てことは、糸絡み予防にもなりますね。
こちらはLED発光で強いハピソンのパンフから抜粋。
ユーザーの写真からも作れるデジタル魚拓の「リフィッシュ」
最近はデジタル魚拓も増えてきて、フルカラーで魚を記録することもできる時代。
そのジャンルも一際光ってたのが、写真から魚拓を作ってくれる「リフィッシュ」でした。
デジタル魚拓の「リフィッシュ」。本物に見えるだろ?これ魚拓(絵)なんだぜ……。
スマホで撮った写真からも加工できるようなので、詳しくはウェブ検索してHPを参考に。
https://re-fish.com
いやもうマジで剥製かと思ったもん。したら絵じゃない? その精彩さに驚きました。カワハギなんて持てそうだったもん。

将来的には3Dデータ化して、個人のVR水槽に入れて鑑賞する楽しみとかありそうですね。
FSは製品自慢9割、技術自慢が1割くらいだったかな
フィッシングショーは釣具店などへの卸売も兼ねているので、商品の見せ方がそんな感じです。
釣具は見るより触れるほうがわかりやすいですけど、本質は魚をかけてからだし、そこで全てを理解して感想をいうのは難しいですね。あくまで所見で終わります。
訪れる人もそれを求めているから、商品展示に人気が集中するし、技術展示や環境保護活動などへの興味は薄そうでした。
CESのような革新技術を披露する場としても、認知されると嬉しいですね。
頑張れ釣具業界!