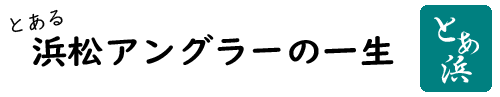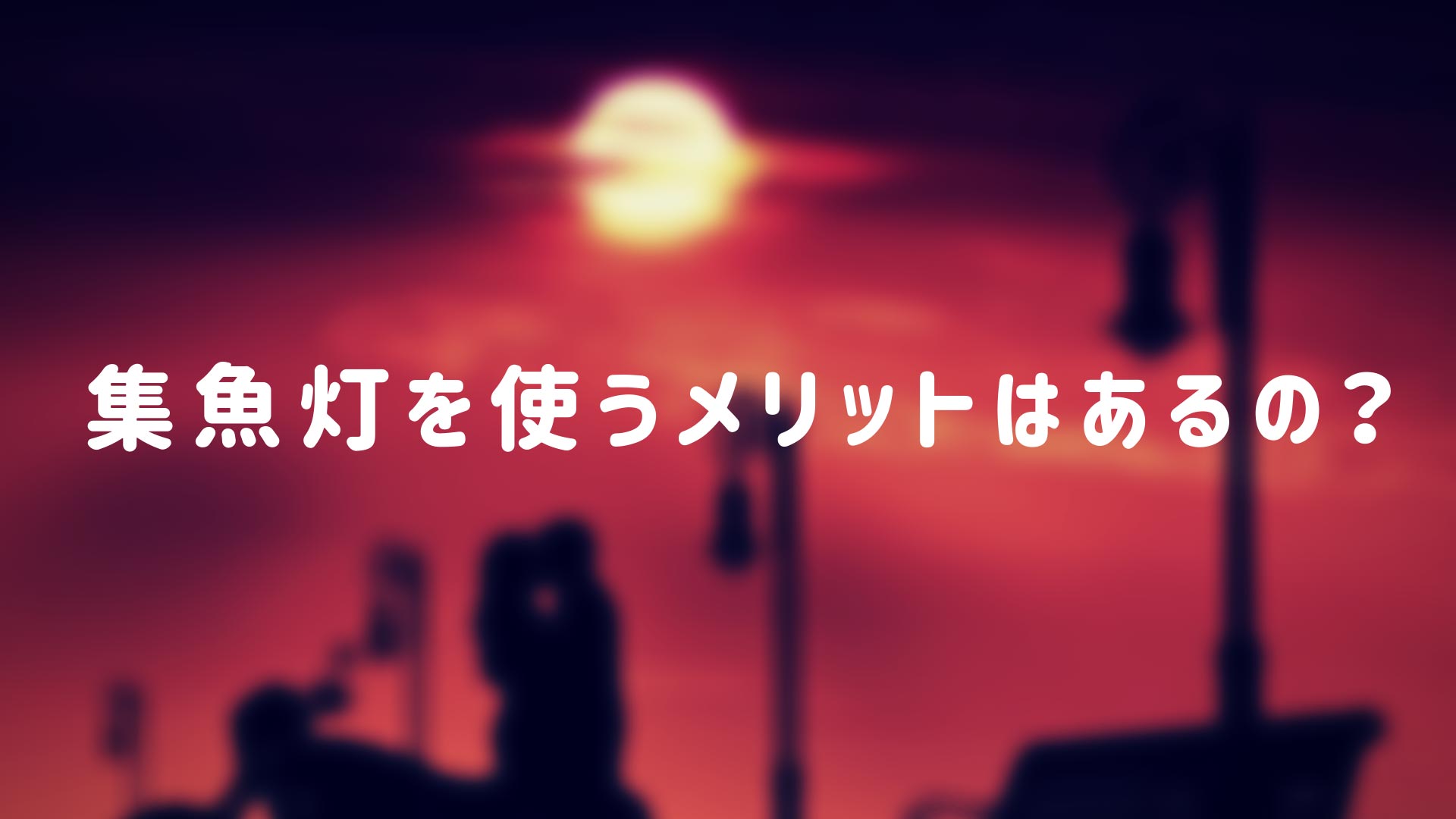堤防釣りの最終兵器と名高い「集魚灯」。
使用すると、フィールド効果でお魚さんが集まります。
ただし、効果が夜限定なのと、近くのアングラーとリアルファイトに発展する確率が上昇します。

────間違ったことは言ってないな!
集魚灯を使うメリットが今ひとつわからない。なので記事を書きつつ学んでみました。
魚はなぜ光の下に集まるのか?
夜の堤防釣りでは、「街灯の下」が良ポイントに挙げられます。
理由は諸説ありますが、特に有力なのは以下の事柄。
- 光でプランクトンのテンションがあがる
- 小魚がプランクトンを見つけてテンションがあがる
- 大型魚が小魚を見つけてテンションがあがる
- 魚が見えるからアングラーのテンションがあがる

人間世界で例えるなら、深夜のコンビニは無駄に人がいるのと同じ。
あらゆる生物は時間ではなく、太陽(日光)の有無で活動時間を決めています。これは遺伝子レベルで決められていること。
夜になって暗くなれば、エサを探すのも難しくなるし、動かずじっとしているほうが効率的。夜に寝る魚もいますしね。
ただし動物は、人間ほど人工光に慣れていません。
真っ暗で寝ていたのに、集魚灯などで照らされたら、「朝か!」と間違えて活動をはじめる可能性もあります。光が眩しくて驚いてしまうほうが適切かもしれませんね。
なにはともあれ、集魚灯などで照らすことにより、水中のアレやコレが活発化するのは間違いありません。
集魚灯で海を照らすと魚が逃げるのでは?
集魚灯には街頭よりも眩しいタイプもあります。

人間が見ても眩しいのに、魚がそれを見たら、近寄らないのでは?
……と思うのも当然のこと。しかし、集魚灯に寄せる必要はないのです。
水中が照らされると、まずはプランクトンが反応して動きます。
その様子を遠くから小魚が見かけて、エサだエサだと喜んで突っ込んできます。
小魚を食べるタイプは、その様子を遠くから待ち構えています。なので、集魚灯を目印に寄ってくるよりかは、集魚灯に小魚が寄ったからこそ効果が期待できます。
よく、ライトで水中を照らすと魚が逃げる話を聞きます。
確かに逃げるんですが、それは驚いてしまっただけのこと。常時照らされている街灯の下では、むしろエサが寄ってくるのを待っている個体もいます。
人工物を上手く利用するのは、夜行型の魚に多いですね。
集魚灯を使うアジングは爆釣するのでは?

集魚灯はアジングなどライトゲームでよく使われますが、波止のタチウオでも使われます。イカちゃんも寄ってきたりするので、わりとなんでも寄せますね。
寄せの効果は人それぞれですし、水中に魚が居るかも影響しますが、その効果についてわかりやすいのは動画でしょう。
Youtubeで検索すると、水中動画も結構あります。
ここで気づいて欲しいのは、集魚灯に照らされている部分よりも、外で待つ魚が多いこと。
だって人間でも、めちゃくちゃ眩しいところには居続けたくはないじゃないですか。
なので堤防のライトゲームに集魚灯を使うなら、光の範囲外を狙うのが鉄則です。光は撒き餌だと思ってください。
- 光に寄るのではなく、光に寄る小魚を目指している
- 集魚灯で照らされている部分より、外を狙うべき(リグが見ると警戒心が増す)
- 集魚灯は夜間の撒き餌だと思いましょう
集魚灯といえばハピソンでしょ
夜釣りに使うヘッドライトといえば「GENTOS」、光る釣具といえば「Hapyson」が浮かぶ。
記事中に、集魚灯を使う際の注意点があります。
地域によっては、釣具として照明の使用が制限されている場合があります。各都道府県ごとに定められているルールやマナーを守ってご使用ください。
詳しくは、水産庁ホームページ『都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)』をご参照ください。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/kisoku/todo_huken/
http://www.hapyson.com/shugyoto/index.php
自前の灯りも漁具に入るため、地域ごとの条例には必ずしたがいましょう。たとえ条例を知らずとも、違反で捕まる可能性はあります。
集魚灯を使う際には、周囲のアングラーに同意を求めましょう。
嫌う人もいれば、「一緒にやろう!(やったぜ)」とフレンドリーな人だっています。余計なトラブルの元は”伝えないこと”。コミュ障であっても、マナーだと言い聞かせるべき。
寄せたい魚に合わせた集魚灯を選ぼう
集魚灯を選ぶ際は、釣りたい(寄せたい)対象魚に合わせたものを選びましょう。主な違いは「色」です。
めちゃくちゃ明るい色に反応しやすい「イカ・タチウオ」がいれば、暗色に近い夕暮れ色は『アジ』が寄りやすい傾向があります。──誤差ですけどね。
購入するなら、少し気にする程度でいいでしょう。
値段もピンキリだし、単独で使える乾電池もあれば、バッテリーを接続する大光量タイプもあります。
明るい色は車用バッテリーなり発電機を使うものもあるけど、乾電池式は安いのがメリット。その代わり、電池の消耗はそれなりにあるので、コスパ的には悪くなります。
発電機を使うタイプは、夜間の工事現場で使うクラスの投光器みたいなもの。
デメリットはうるさいことと、隣人バトルに発展しやすいことですね。
どちらも良いところがあるし、悪いところもあります。