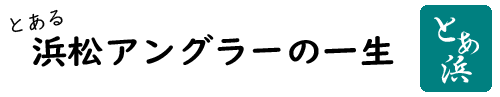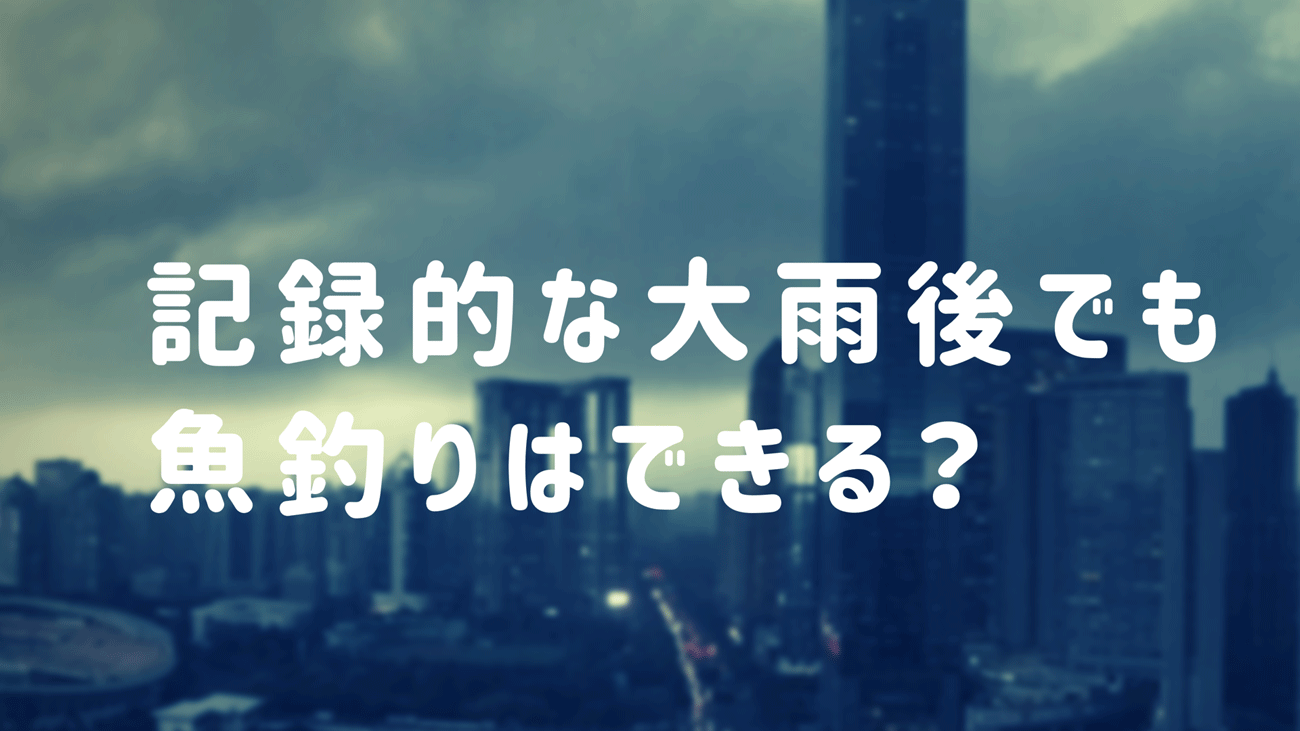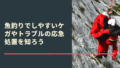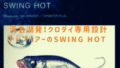近年は長雨や荒天など、異常気象の影響で釣りにいけず、やきもきするアングラーも多いでしょう。
きっと「いつから釣りができるの?」と考えているはず。
答えは──場所による! としかいえません。
大雨後の魚釣りは百害あって一利が奇跡
大雨になると、川は濁流となり、それは海へと流れ込みます。
特に河川はゴミが目立つようになります。
葉っぱや小枝はかわいいもので、稀に大木が流れてきたりするし、それが水底に沈んでいることもあります。海岸でも流れ着いている姿を見ることもあるでしょう。
大雨に魚釣りをすることは可能ですが、沈むゴミに根がかりするリスクは増してしまいます。
それでも君は釣りがしたいのか?
そんなわけで、大雨後に”すぐ”釣りをするのは、無謀といえるでしょう。
──そんなの、そんなのわかっているんだ! 私には、この日しか残されていないんだ!
なんて人のために、記録的な大雨後でも、(諦めなければ)釣りができるかもしれないポイントをピックアップしてみました。
記録的な大雨後でも魚釣りができるかもしれない場所
特別警報が出るような豪雨の後でも、魚釣りができるかもしれないポイントを、確率も交えて表してみました。
- 90%:室内型の釣り堀
- 50%:屋外型の釣り堀
- 30%:湖・池
- 20%:川の支流(上流域)
- 10%:港内
- 100%:ゲーム
ツッコミ所は多々あるでしょうけど、ひとつずつ説明していきます。
大雨後は釣り堀に一抹の希望を託して
釣り堀(管理釣り場)は全天候型の施設が多く、ワンチャンあります。
ただポンド(池)の釣り場は、増水なり流入河川の影響を受けるため、しばらく復旧のために休業とすることもあります。なので事前にHPなりSNSで営業しているか確認しましょう。
探せば屋根有りの管理釣り場もあるので、天候に左右されないメリットがあります。……ただ大物と格闘するのは難しいですね。
以上の条件をもとに、検索サイトで探してみてはいかがでしょう。
湖と池は自然環境でもまだマシなポイント
湖や池は河川流入があるかどうかで変わります。
流入がなければ水位が上昇するだけですし、多少濁りが入る程度で十分戦えます。
河川が繋がっていると、土砂などの濁りが入るし、水質が悪化しやすいため、釣りはできても魚がやる気ないパターンになりやすいですね。
特にダム湖は流木が目立つため、落ち着くまでまちましょう。
注意するべきは、湖や池があるってことは、水が溜まりやすい環境になっていることを、忘れないでください。
釣りはできるが辿り着ける保証がない上流域
河川の源流に近い上流域は、大雨に強いポイントだったりします。むしろ水量が増すことで、上流へ魚が入りやすいことが利点となります。
ただし、土砂崩れや滑落など、命に関わるリスクが高まるため、好んでいく人はぶっちぎりでイカれたアングラーといえます。
ちなみに大雨が降るほど魚が遡上するのは、研究でも証明されています。
当時北海道大学の牧口博士らが10匹のヤマメ(サラマオマス:20-30cm)に発信器をつけたところ、大型台風による大洪水にも関わらず、1匹も流されることなく、いつもと同じ場所に留まっていたそうです。わずか20-30cmの魚が3mを越える大氾濫でもじっと耐えられることに驚きました。この河川は大型の石が多く、逃げ込むスペースが十分に存在したのかもしれません。
https://noah.ees.hokudai.ac.jp/envmi/Itsuro/flood.html
大雨でも源流で魚を釣ることは可能ですが、そこまで行けるかどうかは別の話。降水量で通行止めもありますしね。
港内は流れ着くゴミと濁りでどうしようもない
外洋が荒れていても、港内は比較的安全です。
とはいえ、港は近くに大きな河川があることが多く、多くの倒木や草が流れこみやすい条件も重なっています。
大雨の最中でも釣りができないことはないですが、ゴミで釣りがしにくくなる状況になりやすいです。
水面上のゴミがなくなっても、水底に沈んだ物も多いので、投げ釣りやルアーをやる人は、根掛かりに注意しましょう。
ゲームなら電気があればどこでもできる!
震度7でもゲームをやめられなかった人がいるように、いつでもどこでも釣りを楽しみたいなら、「魚釣りゲーム」の選択もあるのではないだろうか。
この分野は詳しくないため、各自の興味に任せます!(ぶん投げ)

いずれはロッドとリールをコントローラーにした、体験型VRも登場してくることでしょう。
自身の安全と住む場所を守ってから釣りにいこう
気象警報が出ており、緊迫ニュースが流れる中、「明日釣りいけねーなー」と呟くアングラーがいたら、一般人はどう思うでしょう。
いくら同じ釣り人である私でも、「ヤベー奴がいる」と引きます。
まずは自分の安全を確保することが大事。余裕があるなら手助けをしましょう。
気象警報が出ている間は大人しくしているのが最善であり、「様子を見てくる」とフラグを建てるのもやめましょう。釣りにいけないなら、道具のメンテナンスをするとか、学んだりして、時間を有効活用しましょう。